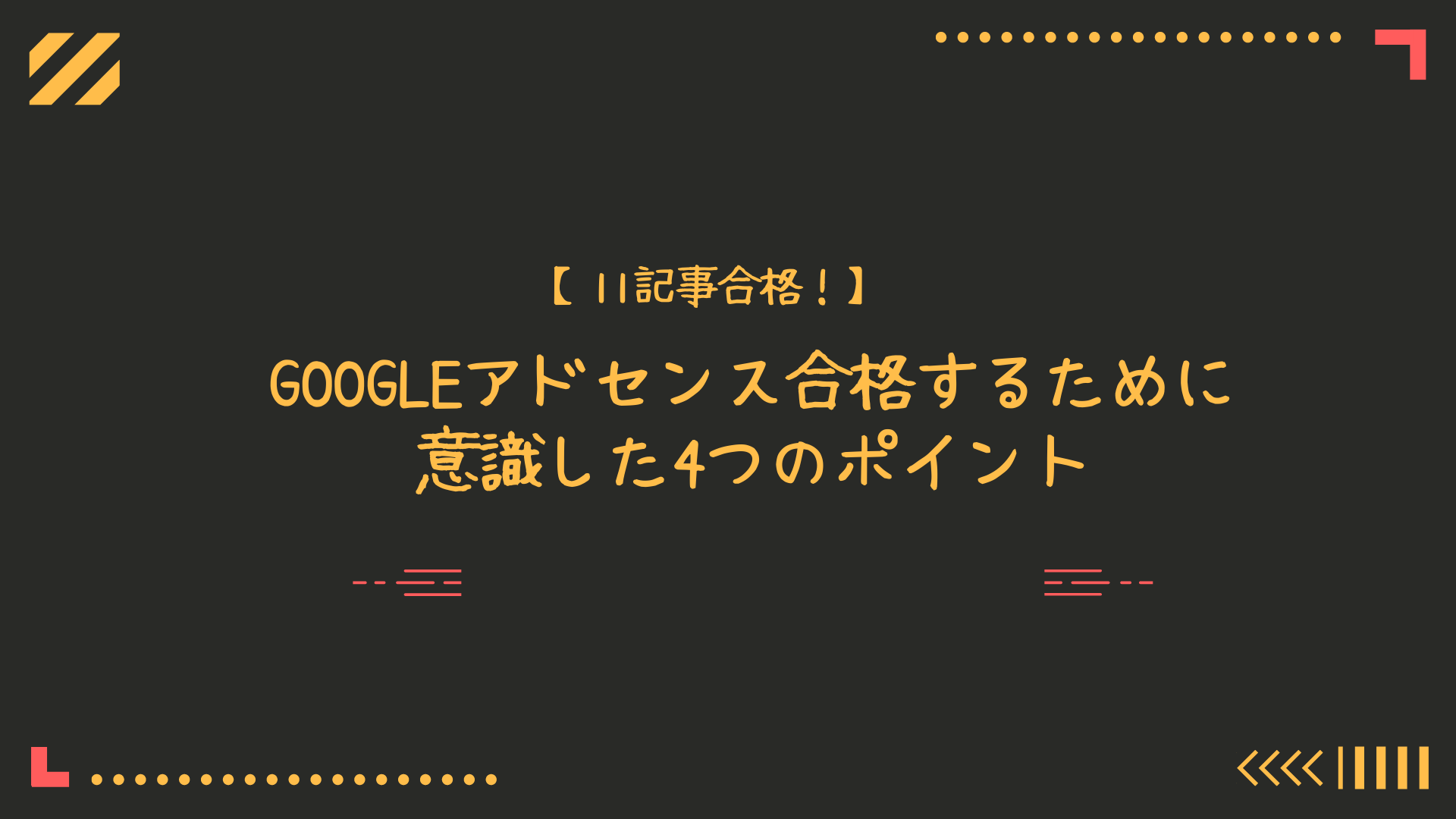・歴史に興味がないので勉強が進まず、全く点数が上がりそうにない。
・そもそも、国語や英語に時間を取られていて、社会に時間を割けない。
こんな悩みを感じたことはありませんか?
これから受験を考える新現役生、昨年のリベンジを誓う浪人生にとって受験科目の選択は志望校選びと同じくらい重要です。
しかし、文系(特に私立文系)の社会科目を適当に選んでしまっている人が多いように感じます。
たしかに、社会といえば歴史(や地理)がメジャーで、政治・経済などの公民分野はマイナーです。
それに、公民分野を選ぼうにも、大学受験で使うための情報はあまりないように感じます。
ただ、マイナーだからといって使えないわけではなく、使い方によっては歴史をも上回るコスパの良さを発揮してくれます。
・歴史は得意じゃないけど、早稲田やMARCHに行きたい。
・国語や英語に追われて時間がないけど、社会科目を一定以上に仕上げたい。
こんな受験生のために、この記事では公民分野の代表である政治・経済を大学受験の視点から解説していきます。
これを読めば、政治・経済が、華々しい大学生活に大きく近づける可能性を秘めた、コスパ最高級の科目であることが分かります!
同じくコスパ最高級である、文系数学に興味がある人はこちらも併せてチェック!⇩
-
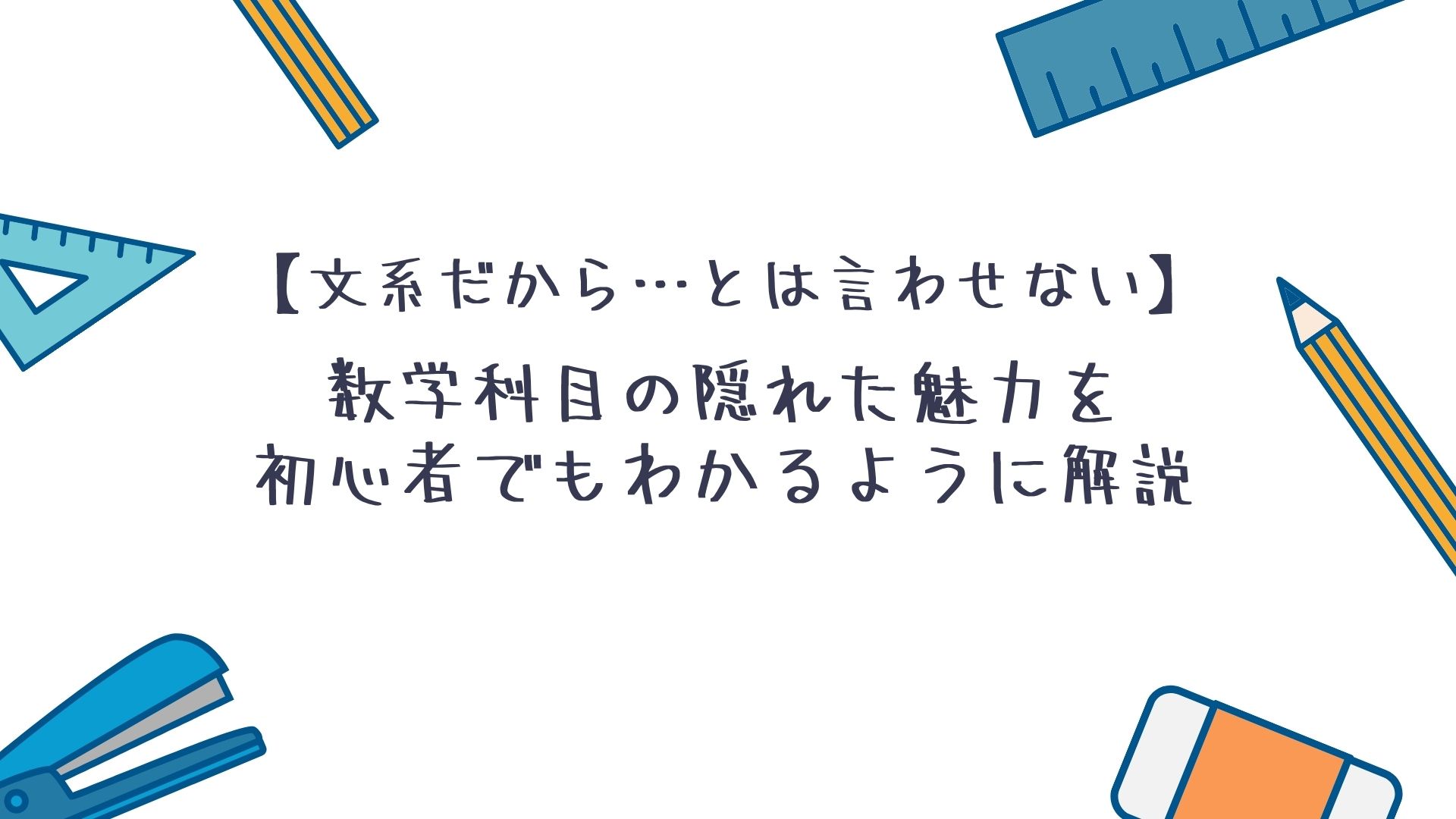
-
【文系数学に興味がある大学受験生必見!】初めての文系数学受験ガイド
文系の大学受験といえば、 「国語・英語・日本史or世界史」が定番で、 毎年多くの文系受験生がこのセットで受験をしています。 一方で、歴史の他に数学を使って受験することもでき、 「国語・英語・数学」で受 ...
続きを見る
1.大学受験で政治・経済を受験するには?
大学受験(特に私立大学)では、数ある科目の中から、3科目を受験し、その得点で合否を判定します。
多くの大学では、国語と英語を必ず受験し、残りの1科目を世界史/日本史/地理/政治・経済/数学から選択して受験します。
例えば、早稲田大学の教育学部(文科系)では、
必須科目:「外国語」(英語)・「国語」の2科目
選択科目:「地歴または公民」(世界史/日本史/地理/政治・経済から1科目)
という形で受験をします。
このとき、選択科目として政治・経済を指定すれば受験できます。
2.大学受験で政治・経済を選ぶのは有利?
2-1.政治・経済で受験できる大学は?
全ての大学で政治・経済を受験できるわけではありませんが、ある程度の大学で受けられます。
毎年多くの受験生に人気である、首都圏の難関私立大学を例にとると、
早稲田大学
・法学部
・教育学部
明治大学
・法学部
・商学部
・政治経済学部
で政治・経済を受験できます。
これらの大学以外にも、立命館大学や中央大学などで受験できます。
2-2.政治・経済で大学受験することのメリットは?
政治・経済を受験することのメリットは、主に2つあります。
①歴史科目に比べて対策しやすい。
政治・経済は歴史科目に比べて、圧倒的に覚える用語の量が少ないです。
各科目の用語集(山川出版社から出版)に収録されている用語数を基準に比較すると、
世界史:約5600語
日本史:約10700語
政治・経済:約3100語
となっており、政治・経済の用語数は歴史科目の30~50%です。
つまり、単純計算で覚える時間も1/3~1/2で済むこととなり、より短時間で問題演習に取り掛かれます。
さらに、政治・経済で扱う政治形態や経済システムは、普段のニュースで目にすることも多く、具体的にイメージしながら覚えられます。
そのため、ニュースに敏感であれば、生きたニュースを題材に覚えた内容をアウトプットできます。
時事問題の対策をしつつ、問題演習につながるアウトプットが普段からできると、非常に効率よく勉強を進められます!
②テストの点数が伸びやすい。
先ほど述べたように、政治・経済は覚える量が少なく、問題演習により早く取り掛かれます。
大学入試の問題を見てみると分かりますが、MARCHレベルであっても基本用語の穴埋めが多くを占めています。
また、記述問題も出題されますが、歴史科目に比べて簡単で、基礎的な説明ができれば十分点数は取れるようになっています。
つまり、問題形式に慣れやすく解ける問題が増えるため、模試などのテストで手っ取り早く点数を上げられる可能性があります。
さらに、応用レベルにレベルアップしても、覚える用語が倍増したり、難問奇問が増えたりすることはあまりありません。
そのため、政治・経済を得意科目にしている人は、明治大学レベルでほぼ満点を取ることも可能です。
これは、受験生活を送る上でもいい影響を及ぼします。
例えば、政治経済が得意科目となり、政治・経済にかける時間が日あたり1時間短くなったとしましょう。
この1時間を国語や英語の苦手な分野の対策に使ったり、1時間早く勉強時間を終えて、趣味や好きなことに時間を使えたりします。
そして、毎日1時間短くなれば、
1週間で7時間
1ヶ月で約30時間、
余裕ができる計算になります。
それだけの時間があれば、受験勉強しながら別のことに打ち込んだり、苦手科目を克服することができるでしょう。
これによって、点数が伸びないことへの焦りや、受験勉強が単調で面白くなくなることはかなり少なくなるはずです。
2-3.逆に、デメリットは?
これらのメリットがある反面、政治経済を選択することにデメリットもあります。
①受験校によっては対策が大変。
メリット①で、政治・経済は、覚える量が少なく問題慣れしやすいため、対策が容易であるといいました。
確かにこれは正しいのですが、早稲田レベルになると少し話が変わってきます。
早稲田レベルでも、形式は穴埋めや多肢選択が多い一方、問題の内容が少し発展的になっています。
例えば、年号・割合・法律・判例の知識が少し詳しく問われたり、選択肢もすぐには判断が難しい内容になっていたりします。
このレベルで合格点以上を取るには、MARCHレベルから追加で1冊以上の参考書をやる必要があり、演習に時間がかかります。
また、時事問題の対策もGMARCHレベルより重要になり、問題演習+αの勉強時間と労力がかかってしまいます。
さらに、早稲田レベルは国語や英語の対策も時間がかかるので、政治・経済のコスパの良さはあまり感じられないかもしれません。
②希望する大学(学部)が受けられないかもしれない。
2-1でも触れましたが、政治・経済をすべての大学で受験できるわけではありません。
慶應義塾大学・・・すべての学部で政治経済の受験✕
早稲田大学・・・教育学部では政治・経済の受験✕
といったように、大学によって全部または一部の学部で受験できないケースがあります。
原則として、GMARCH以下の大学では政治・経済を受験できるようです。
しかし、例外もあるため、あなたが志望する大学(学部)で政治経済を受験できるかは要チェックです!
3.大学受験で政治経済を選ぶべきなのはこんな人!
以上を踏まえて、政治経済がオススメな人はこんな人です。
3-1.ニュースに興味がある人
政治・経済で学ぶ内容は毎日のニュースの基礎であり、ニュースに関心があれば勉強しているときにもイメージしやすくなります。
また、政治・経済で出題される時事問題も、話題になったニュースに目を通しておけばある程度は対応できます。
よって、日頃からニュースになじみのある人にとってはゼロからでも勉強を進めやすい科目といえるでしょう。
3-2.時間がない人
政治・経済は、短時間で対策できるため、「高3の9月から勉強しはじめても間に合う。」といわれるほど時間がない人におすすめです。
実際、夏ごろまで歴史をやっていたが点数が上がらず、政治・経済に切り替えて合格できた受験生もいます。
また、国語・英語の対策に時間がかかり、社会は時間がかけられないといった受験生にも、政治・経済は有効といえるでしょう。
3-3.歴史にしっくり来ていない人
「私文といえば歴史(特に日本史)選択!」が定番となっており、ほとんどの受験生は歴史科目を選択しています。
しかし、歴史を選択したはいいものの、用語を覚えられなかったり、覚えても点数に結びつかなかったりして苦しむ受験生は毎年います。
苦しんだ末に点数が上がればそれでいいのですが、多くの受験生は点数が伸び悩んだまま受験本番を迎えます。
そんな人にこそおすすめしたいのが、政治・経済。
何度も言いますが、政治・経済の特徴は最低限の対策でも点数も上がりやすいことです。
これを活かせば、悩みの種であった社会科目が一気に得点源となり、合格に大きく近づけるでしょう。
4.大学受験の政治・経済は優良科目!
これまで、大学受験の観点から政治・経済の基本的な特徴を説明してきました。
政治・経済も社会科目なので、覚えるべきことは一定数ありますし、その暗記も簡単ではありません。
しかし、容易にイメージしながら学べて点数も上がりやすいというメリットがあり、コスパは社会科目NO.1といえます。
ただ、志望大学によって選択に注意する必要があるというデメリットがあるため、あなたの志望と相談してほしいですね。
ここまで読んでくださったあなたに少しでも政治・経済の魅力が伝われば、この記事を読んだ価値は十分あります。
コスパ最強科目の一つである政治・経済。
あなたもそのコスパの良さを体験して圧倒的な合格をゲットしてみませんか?